|
朝起きたら女になっていた 。
それは本来男としてこの世に生を受けたはずのヒュンケルにとって、慌てふためく非常事態だというのに、当の本人は特に動揺することなくベットから起き上がると、顔を洗うため洗面所へと消えていってしまった。
元々感情表現が少ないヒュンケルだが、なぜ彼がこんなにも落ち着いていられるのかには理由がある。
それはこの性別が変わってしまうという非現実的な出来事が、最近は日常茶飯事になりつつあるからだった。
ヒュンケルが仕えるここパプニカの王女レオナは、兎に角退屈な事が嫌いな悪戯好きの面白い事好きという性格から、時々度肝を抜くようなとんでもない事態を引き起こす事がある。きっと今回もそれが原因に違いない……。
(…またあの姫の仕業か…)
冷たい水で顔を洗い本来なら清々しい気分になるはずが、逆にどんよりと重い気分のまま部屋に戻ったヒュンケルは、隅に置かれている大きなクロ―ゼットの前まで歩いて行った。
物に対してあまり執着心のないヒュンケルの部屋には、今まで必要最低限の家具や荷物しか置かれていなかったのだが、数日前からこの大きなクロ-ゼットが置かれるようになった。
(…さて、今日はどれを着ればいいのか…)
無言でそのクロ-ゼットを開けたヒュンケルの目に、色とりどりの洋服が飛び込んでくる。
フリルやレ-スをふんだんに使った可愛らしい洋服から、シックで大人っぽい服まで兎に角沢山の洋服で埋め尽くされたクロ-ゼットの中から、ヒュンケルは比較的シンプルな紫のチャイナ服を手に取りそれを着る事にした。
男であるはずのヒュンケルの部屋に、なぜこんなにも大量の女性用の服があるのか不思議に思うかもしれないが、実はこの服及びクロ-ゼットは、レオナからのプレゼントだったりする。
『女の子になった時に着る服がないと不便でしょ?』
そんな言葉と共にレオナはクロ-ゼットいっぱいに服を詰めてヒュンケルにプレゼントしてきたのだ。
別に男性用のサイズの小さい服を着るからいいと言ったのだが、「なによそんなの全然可愛くないじゃない!」と言い機嫌を悪くしたレオナに、あれやこれやと八つ当たりを受けるようになったヒュンケルは、渋々女性物の服を着る事にしたのだった。
そんな迷惑な服に着替えたヒュンケルは、これまた服と共布で作られた靴を履き、元に戻るための解毒剤を貰いにレオナの執務室へと向かった。
*************************
コンコン・・・
「失礼します。」
「・・・・・・」
「姫、失礼します。」
「・・・・・・」
レオナの執務室の前で軽く扉をノックするものの、室内からの返答がない事にヒュンケルは首を傾げた。
(…おかしいな…今日の午前中は執務室で書類を仕上げると言っていたのだが…)
一瞬出直そうかと思ったが、一時間後に兵士達との鍛錬がある事を思い出したヒュンケルは、少々不躾だと思いつつも室内で待たせてもらう事にした。
もう一度「失礼します」と声を掛け入った室内には、やはり誰もいなく…と思いきや、部屋の奥、明るい日差しが差し込む窓際近くに誰かが立っているのが見えた。
「…姫…?いらっしゃったのですね、これは失礼致しま…」
「…なんだ貴様は…」
「え…?」
てっきりレオナだとばかり思っていたヒュンケルは返ってきた声に驚いた。
「…何か用か?」
「あ!」
少々苛立ちを含んだ声で窓際から姿を現した人物に、ヒュンケルは二度驚きの声を上げてしまった。
「お、おまえは…」
なんとそこに立っていたのはヒュンケルもよく知る親友 ラ-ハルトだったのだ。
いつもダイの補佐役兼保護者として、常に傍に付いているはずのラ-ハルトがなぜレオナの執務室にいるのか一瞬疑問に思ったが、どうやら手に書類らしき物を持っている。
きっと朝一でレオナに提出する書類を持って来たのだろう。
そんな事を考えていたヒュンケルだった、はたと自分の今の姿を思い出し青くなった。
(…流石にラ-ハルトとはいえ、このような姿見られたくはないな…)
いくら女になったとはいえ、中身は男であるヒュンケルは、やはり女性物を着た自分の姿を親友には見られたくないと思った。
幸いラ-ハルトからは己の姿がはっきりとは見えていないようなので、気付かれる前に部屋を後にしよう…と、そっと足を扉へと向けた時だった。
「おい、貴様何か用があったのではないのか?その様にこそこそと…怪しいな…」
咄嗟に部屋から出ようとした姿が怪しく映ったのか、ヒュンケルはラ-ハルトに呼び止められてしまった。
そのうえ強引に腕を捕まれたかと思うと、ヒュンケルは勢いよく正面を向かされてしまった。
「…やはり貴様怪しいな…顔を上げろ!」
そう言うと少々乱暴にヒュンケルの顔を上げさせるラ-ハルト。
「っ痛!!」
乱暴な行為にヒュンケルの顔が苦痛に歪んだが、それ以上にヒュンケルを見たラ-ハルトの顔が一瞬驚きに変わったかと思うと、みるみる真っ赤に(正確には青黒く)染められていく。
「お、お前はあの時の…!!」
そう言うと急に顔色を歌変え、わたわたと慌てだしたラーハルトに、今度はヒュンケルが不信感を抱く番だった。
いつも以上に悪い顔色と、「あ」とか「う」とか意味不明な言葉を発し、目はあちらこちらとさ迷い、決してヒュンケルと目を合わせようとしない。
(…なにをラ-ハルトはこんなに慌てているんだ…?)
そんなラーハルトに益々不信感が募るヒュンケルだったが、きっといくら考えたところでヒュンケルにはわかるはずもない事だった。
そう、ヒュンケルは知らないのだ。
数日前、たまたま女性の姿のままレオナ、ダイ、ポップと4人でいる所にやって来たラ-ハルトが、女になった自分の姿を見た瞬間、一目惚れしてしまったなど、きっと言ったところで信じないだろう。
あの時はパニックのあまり情けないほど我を忘れて部屋を飛び出してしまったラ-ハルトだったが、今回の突然の再開でもあの時と同様パニックに陥っていた。
とりあえず前回の様に飛び出して行かないだけマシになったと言うべきか…。
だがその姿は彼を知る者が見ればかなり滑稽に見えたであろう……。
現にそんな2人をこっそり眺めつつ、必死で笑いを堪えている者がいた。
『っぷ、ははは!!あのラーハルトがあんなに慌ててるわよー!傑作だわ!』
『ひ、姫さんそんなに笑っちゃプッ!!2人に悪いって!ぷっははー!』
執務室の一角に造られた王族専用の書庫から微かに漏れる笑い声…。
それは一人はパプニカ王国一のお騒がせ王女レオナ、そしてもう一人は魔法使いのポップの声だった。
2人はヒュンケル達が部屋を訪れる少し前にこの書庫にいたのだが、目的の物も見つかりさて、書庫から出ようと扉を開けた瞬間、偶然にも慌てふためくラ-ハルトと、それを不思議そうな顔で見詰めるヒュンケルの姿を目撃してしまったのだ。
前々からラ-ハルトが女ヒュンケルを好きな事を知っているレオナとポップからすれば、当然2人の今後の展開が気になったのであろう、お互いなにも言わなくとも、そっと開いていた書庫の扉を閉じ、次にすこ~しだけ開くと、中の様子を盗み見ていたのだった。
『しっかしあのラーハルトが恋とはホントびっくりだぜ。』
『私もよ。あの人ほど恋に無縁な人はいないと思ってたけど、世の中わからないものよねー』
『しかも相手はいくら女とはいえあのヒュンケルだろ?本当の事知ったら絶対ラ-ハルトの奴落ち込むだろうな…』
『そんなの内緒に決まってるでしょ?あんなラ-ハルトを見られるのなんて一生に一度有るか無いかなのよ!?……まー手遅れになる前には教えてあげるつもりだけど、もう少しぐらい楽しませてもらったって罰は当たらないはずよ!』
そう言うと改めて食い入るように室内の様子を覗き込むレオナ。
『ははは…ま、確かにそれもそうだけどよー、あんま心のキズが深くなる前に教えてやろうぜ…』
やんわりラ-ハルトを庇う発言をしつつも、レオナに釣られ室内へと視線を戻したポップだったが、相変わらずラーハルトは挙動不審のままと、変わらない状態が続いていた。
『…何か…いい加減何か喋ってくれないかしら…。全然変化がなくてつまんないんだけど…』
元々短気なレオナはあまりのラーハルトの変化の無さに、だんだんと苛立ちを募らせていた。
『んー確かに…。でもあのラ-ハルトだぜ?最初っから何か期待したところであいつじゃ無理があったのかもなー』
『…まぁ、それもそうだけど…だからってせめて一言ぐらい何か喋ったって良いと思わない?あのままじゃ時間の無駄よ!』
『そうは言うけどあいつじゃ無理じゃねぇかなぁー』
『でも…!』
半分諦めム-ドになってしまっているポップとは裏腹に、レオナはまだこれからの展開を諦めきれないのか、尚も食い下がってくる。
だがそんな時、少々乱暴に扉を叩く音がした。
ドンドンドン・・・!
『…お?誰か来たみたいだぜ?』
『もう、誰よこんな時に!』
突然の訪問者に苛立ちを隠せないレオナだったが、後々この訪問者によって自体は思わぬ方向へと進むなど、この時誰が想像できただろうか…。
「ちーす!姫さん?ちょっとはえーけど邪魔するぜー!」
バタン!と勢いよく扉を開け、室内へと入って来たのは皆がよく知る金属生命体のヒムだった。
「き、貴様!いつの間に入ってきた!」
ノックの音にまったく気が付かなかったラ-ハルトが、驚きの声を上げるものの、ヒムはまったく気にする事無くずかずかとラ-ハルトに近づいてきた。
「あぁん?つい今さっきだよ。って…おめえはラーハルトじゃねぇか!いやー久振りだな!元気してたか?」
久しぶりの知り合いとの再開に喜ぶヒムは、バンバンと遠慮無しにラ-ハルトの肩を叩いてくる。
「ふ、ふん!貴様に心配されるような事はなにもない!」
「けーっ!相変わらず突っ張ってんなぁー。ま、それはいいとして、姫さん知らねぇか?」
そう言うと室内をきょろきょろと見渡す。
『…姫さん、なんかヒムに用事でもあったのか?』
『…えぇ。彼に頼みたい仕事があったんだけど…予定ではもう少し遅くなるって聞いていたのに、思ったより早く着いちゃったみたいね…タイミング悪いわ…』
折角2人っきりだったのに残念~という思いが滲み出ているレオナだったが、自分から呼び出しておいて来客を待たせるのも失礼かと思い、諦めて書庫から出ようとした時だった。
「あれ~?おめえは誰だっけ?」
ラーハルトの後ろ、無言で佇むヒュンケルを見るやヒムは不思議そうに声を掛けた。
「なんか見た事有るような無いような顔だけど、姫さんの侍女だったか?」
軽く首を傾げ記憶の糸を手繰り寄せるヒムだったが、どうにもこうにも思い出せない。
だがなぜかこの女性とは初対面とは違う、なにかこう懐かしさといったものを感じたヒムは、ついつい無意識の内にヒュンケルを熱い視線で見詰めてしまっていた。
(な、なぜだろう…ものすごく居心地が悪い…)
元々人に注目される事が苦手なヒュンケルは、これでもかと凝視してくるヒムに、なんとも言えない羞恥が込み上げてくるのを感じた。
どっかのエロ魔法使いとは違い、ヒムはただ単に己が誰なのかを思い出す為に見ているだけだとわかっていても、やはりまじまじと見詰められるというのはなにか恥ずかしい…。
それにラ-ハルト同様、自分の事をライバルだ友だと思っているヒムに、己のこんな姿をじろじろ見られるのは嫌だし、正体がバレるのはもっと嫌だ。
「あ…その…あまり見ないでくれるか…」
恥じらいに耐え兼ねたヒュンケルは、そっと腕で身体を包むと、白く美しい頬を桃色に染め、しおらし気に俯くと、なんとかヒムの視線から逃れようとした。
だがその行動、仕草がなんとも愛らしく、そして同時になんともいえない色気をも醸し出していた事に、ヒュンケルは気付かない。
とくん……
そんなヒュンケルの一連の動作を見ていたヒムの心臓が、本人の意思とは関係なく小さく高鳴ったかと思うと、それはみるみる大きな音へと変わり、更には頭に血が上り頬が熱くなってくる。
そして同時に今まで感じた事のない甘い疼きが全身を駆け巡った。
(おいおい、急にどうしたんだ俺の身体は…?!)
未だかつて体験した事のない身体の変化に、戸惑いを隠せないヒムだったが、目だけはヒュンケルを捉えたままどうしても逸らすができないでいた。
(…そういやーこいつ…よく見るとすげー綺麗な顔してんなぁ…それに無駄のまったくねぇこの身体つき…まるで戦士みてぇだぁ…)
逸らせない視線のまま、熱く血が上る頭でヒムはぼんやりそんな事を考えていた。
今まで人間の女の顔だの身体だのに興味をもった事などないヒムだったが、今はなぜか目の前の女が気になってしょうがない…。
(…なんだってこんなにこいつの事が気になるんだ…?)
回らない頭であれこれ考え始めたヒムだったが、それはすぐにやめた。
頭で考えるなど自分には合わないとわかっているヒムは、実にストレ-トに今の自分の気持ち、状況をヒュンケルに聞いてみる事にした。
「なぁ、突然で悪いんだがよ、俺おまえ見てるとすっげー胸がドキドキする上に、おまえが気になって目が離せねぇんだよ…これってなんでかわかるか?」
そんな事を超真剣な顔でヒュンケルに聞くヒム。
「…はぁ?」
いくらヒュンケルに関する事とはいえ、ヒム自身にわからない事が、どうやってヒュンケルにわかるのだろう…。
案の定ヒュンケルはというと、ヒムの疑問も、言葉の意味もわからないと首を傾げている。
しかし、ヒュンケルの隣、ラ-ハルトだけは、急にぴたりと止まり、表情を険しくした。
「だーかーらー、なんでおまえを見てるとこんなに頭に血が上ったり、頬が火照ったりするんだ?それに無性になぜかおまえを抱きしめたくなるんだが…」
「えぇぇ!?」
その言葉には流石のヒュンケルも驚きの声を上げた。
そしてその横、ラ-ハルトも益々表情を険しくしたか思うと……
ピシィ・・・・・
つるんとしたおでこに、でかでかと青筋を浮かべ、恐ろしいまでの形相へと変わったラ-ハルトは、突然ぶるぶると震えだした。
「お、おい!ラ-ハルト?大丈夫か?なにをそんなに…」
震えているんだ?と、言いかけてヒュンケルは止まった。
ラ-ハルトがなぜ震えているのか、聞かなくともその表情が全てをものがたっていたのだ。
一体なにがラ-ハルトをこれほどまでに激怒させたのか、まったくわからないヒュンケルは、困ったようにオロオロしている。
一方、そんなヒュンケルやラ-ハルトの様子を、書庫に隠れて見ていたレオナとポップは、ヒムの言葉にあんぐりと口を大きく開け、驚いていた。
だって、だってそれは……
“恋”
と、いうものではないのか…と、ヒムとヒュンケル以外の3人は心の中で叫んだ。
『ちょっと何を言い出すかと思えば愛の告白!?もう信じられないわ!』
執務室の隣、書庫ではレオナが興奮のあまりスカ-トを翻しばたばたと暴れている。
姫君ともあろう方がはしたない!と、城の者が見れば注意の一つもしたかもしれないが、あいにく今ここにいるのはポップただ一人。
そんなポップも、突然のヒムの告白ともとれる台詞に大いに驚いていた。
『おいおいマジかよ!あいつまでヒュンケルに惚れちまったのか!?』
『ラーハルトに続きヒムもってことは…これって三角関係ってことよね!?や~ん燃えるわ~!』
三度の飯より恋話が好きなレオナは、既に3人の三角関係図を勝手に想像し一人で盛り上がっている。
だがそんなきゃいきゃいとはしゃぐ書庫のメンバ-とは裏腹に、執務室のラーハルトといえば、怒りと同時に心に大ダメ-ジを受けていた。
(ま、ま、まさかこいつもこの女の事が好きだったとは…!)
ヒム自身まだその自覚はないようだが、あの台詞を言ってしまった以上、それは愛の告白をしたのも同じ。
そしてそれは彼女に好意を寄せるラーハルトにとっては、宣戦布告されたも同然だった。
『ライバル出現…!』
そんなテロップがでかでかとラ-ハルトの頭上に出現したかと思うと、すぐさま音を立てて崩れ去っていく。
そして次に現れたのは、勝ち誇った顔のヒムと、そんなヒムに寄り添うラーハルトが愛してやまない女性の姿…。
((ぎゃー!!やめろー!!))
ただの想像だというのに、痛恨の一撃を食らったかの如く大ダメ-ジを受けたラーハルトはその場に崩れ落ちそうになった。
自分で想像しておきながらなんだと思うかもしれないが、どう考えたってラーハルトとヒムではラ-ハルトに分が悪過ぎるのだ。
これは悲しいかなラ-ハルト自身も理解している事で、普段から無口無愛想無感情の自分とは違い、ヒムは少々荒っぽいところは有るが、さばさばした性格に明るくよく喋り、情も厚い、そんな相手と恋のタイマン張ったところで、勝敗など目に見えている。
奴が金属生命体だからといって、人とは結ばれないとは限らない。まだまだ金属生命体には謎が多いのだ。
それに奴ほど人間に限りなく近い生命体などいないだろうし、自分とて半魔族であって人間ではないのだ。
顔は申し分ないほど整っていても、ただ黙って立っているだけで、なんとなく怒っているのではないかと、勘違いされるラ-ハルトよりも、異質な姿をしているとはいえ、明るく気さくなヒムの方が、女性からは人気があるのだ。
(く…奴には敵わんかもしれんが…だが俺は諦めん…!!)
負ける事が大嫌いなラ-ハルトは、戦いだけでなく恋にもその思いは反映され、不利な状況下でも決して諦めようとは思わなかった。
それが圧倒的状況下であったとしてもだ。
今、目の前で馴れ馴れしくヒュンケルに話しかけるヒムに(※ラ-ハルトにはそんな事は到底できない)メラメラと嫉妬の炎を燃やす。
「打倒ヒム!」を心に刻んだラ-ハルトの瞳は、すでに恋に狂わされた哀れな男のものだったとか……。
*************************
『…なぁ姫さん、どっちに賭ける?』
『う~んこのままの状況ならヒムに一票…でもあのラ-ハルトが何もしないとは考えられ無いわね…』
『あぁ、それにラーハルトのあの顔、絶対なにか決意した顔だぜ。』
『フフフフ…ま、どちらにしろ面白くなる事には間違いないわね♪』
『あぁ、違いねぇ♪』
そんな3人を余所に、書庫では大いにこの状況を楽しんでいるレオナとポップの楽しそうな声が響いたのだった。
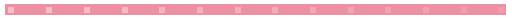
|