|
その時まで何も変わらない平和で穏やかな一日になると思っていた 。
「ん……あぁ…もう朝か…」
大きな窓から差し込む柔らかな光に、ヒュンケルは軽く瞬きをすると寝床から起き上がった。
「…さて、着替えて朝練にでも行くか…」
ふるふるっと頭を振ると、ボ-としていた頭に血が巡り冴えてくる。
軽く伸びをし、窓辺まで歩くと朝日の差し込む窓を大きく開け、朝の空気を胸いっぱいに吸い込んだ。
瑞々しい新鮮な空気は、それだけで気持ちが良い。
あぁ…今日も一日平和で良い日になるだろう…
そんな穏やかな気持ちでいっぱいのヒュンケルを、この後災難が待ち受けているなど、誰が予想できただろうか…。
一頻り朝の空気を堪能したヒュンケルは、朝練に行くため軽く身支度を整えると部屋を後にした。
通り慣れた廊下を、これまたいつもと変わらぬ歩調で歩き調練場へと向かったヒュンケルだったが、一つ目の角を曲がった時、己の身体の異変に気がついた。
(…ん…?なんだこの胸の違和感は…)
ヒュンケルの胸をきゅ…っと何かが圧迫するような感じ……
最初は気のせいかと思うほど些細な圧迫感だったが、しばらくするとそれは気のせいとは言ってられないほど激しさを増し、ついには呼吸すらままならない状態に陥ってしまった。
「…っく、苦しい!!…な、なんだ一体!?」
ぎゅうぎゅうと締め付ける力は増す一方で、とうとうヒュンケルは耐え切れずその場に膝を着いてしまった。
(い、一体なんだこの胸の苦しみは!!お、俺の身体はどうなってしまったんだ…!?)
額に脂汗が滲み出てくるのを感じつつ、ヒュンケルは震える手で上着を握り締めた。
この苦しみから少しでも逃れる為に、上着のボタンを外そうとしたのだ。
だがその瞬間 !
ブチッーー!!
「!!!?!!?」
激しい音と共に何かが勢いよく飛び散った…かと思うと、あんなにも激しかった圧迫感が嘘のように消えてしまった。
「な、なんだ今のは…」
ゼェーゼェーと荒い息を吐くヒュンケルだったが、一先ず胸の苦しみから解放された事に安堵し、ほぉーと胸を撫で下ろした時だった…
ムニ……
手になにか弾力のある物が当たったような気がする……
(……ん……?)
プニ…プニ……
(………………)
まるでスライムに触れているかのような、柔らかくそれでいて適度な弾力がある不思議な手触り……。
己の身体にそんな柔らかな部分が存在したのか…そう疑問に思ったヒュンケルが、恐る恐る今自分が触れているであろう部分を見た瞬間、一気に顔色を失った。
わなわなと震えるヒュンケルの視線の先 ・・・
その先には大きな膨らみが2つ…ぷるるん♪と大きく揺れていた。
そう、それは誰がどう見ても正真正銘立派な女性のおっぱいであったのだ。
「な、なぜこんなモノが俺の身体に…!」
あまりの衝撃に、前を隠すのも忘れてヒュンケルはうろたえた。
本来男であるはずの自分には存在しないはずのモノが一体なぜ…!?
そう心の中で自問するものの、明確な答えは浮かんでこず、だからといってこれは夢だと思うには余りにも生々し過ぎる感触だ。
(一体俺の身体に何が起きたというのだ…!)
しばらくその場で途方に暮れていたヒュンケルだったが、よくよく今自分が置かれている状況を考え更に青くなった。
なぜなら今ここはパプニカの城の中で、更に言えば人々が行き交う廊下のど真ん中(※今は早朝の為誰もいないが)そんな場所で胸元を全開にしたまま突っ立っているという状態は、あまりにも風紀上よろしくないのではないか……下手をすればわいせつ物陳列罪で捕まってしまうかもしれない ・・・
(そ、それは困る!!兎に角胸元だけでも隠さなければ…!)
あわあわと慌ててボタンを留めようとするものの、なぜか肝心のボタンが見当たらない。
元々ボタンが留まっていたであろう箇所には、引き千切られたかのように糸がだらりと下がっているだけだ。
(…っな!…ボタンは何処へいってしまったのだ…!?)
慌てて辺りを見渡すと、廊下の隅にボタンらしき物が転がっているのを見つけた。
(あんな所に…!)
急いで駆け寄り拾い上げ、更に周りを見渡し他のボタンを探す。
幸いな事に直ぐにいくつかのボタンが落ちているのが見つかった。
(あぁ…よかった。しかしなぜこんな所に転がっているんだ…?)
拾ったボタンを不思議そうに眺めていたヒュンケルだったが、ふとある事を思い出した。
そう、それは先程の何かが切れる大きな音……
そして音と共に何かが一緒に飛んでいった様な気がする…
(…そ、そうか!あの時の音はボタンが千切れた音だったのか!)
ヒュンケルが上着による胸の圧迫感に苦しめられていた時、きっとボタンはボタンでなんとか引き千切られないようにと必死だったのだろう。
だがとうとう膨らみに耐え切れなくなったボタンは、ブチッ!という音と共に飛んで行ってしまったのだ。
「だからボタンがないのか…」
ようやくボタン行方不明の真相に辿りついたヒュンケルだったが、まだ重大な問題が残っている事を思い出した。
「そ、そうだ!早くこの身体を元に戻さねば!」
再びあわあわとこの奇妙な現象について考え始めたヒュンケルだったが、考える内にある一つの可能性へと辿り着いた。
それは忘れもしない数ヶ月前の事・・・・・・
退屈しのぎにレオナが発明した、飲むと性別が変わってしまうという不思議な薬の事。
ヒュンケルはその薬をレオナに無理やり飲まされ、女にされてしまった事があったのだ。
その時はなんだかんだ言って解毒剤を貰い元に戻る事が出来たのだが、姫の手元に薬がある以上、いつ何時また使われても不思議はないはずだ。
きっと今回だって、暇を持て余した姫が薬を使って己をからかおうとしたに違いない。
(…そうだな…間違いない…!)
そう確信したと同時にヒュンケルは全ての元凶であるだろうレオナの元へと急いだ。
*************************
「あら、ヒュンケル案外遅かったわね、待っていたのよ?」
勢いよく部屋へと飛び込んで来たヒュンケルを、それはそれは優雅で上品な笑みを浮かべたレオナが迎えてくれた。
「あ、ヒュンケル!待ってたよ!」
「おう!ホント待ちくたびれちまったぜー」
室内にはレオナだけでなく、ダイとポップまでもがヒュンケルを待っていたようだ。
「…お前達どうして此処に…」
「えっとレオナがね、女の子になったヒュンケルを見せてくれるって言ったから来たんだー」
「なに!?」
無邪気な笑顔でそう答えるダイに、声が裏返るほどヒュンケルはびっくりした。
「この前のパ-ティ-で女のお前を見損ねちまったって姫さんに話したら、もう一度見せてあげるって言われて今日こうして待ってたってわけだよ」
「…それは本当ですか姫…?」
「本当よーだってあのヒュンケルを見れなかったなんて、2人とも可哀相じゃな~い」
「か、可哀相って…そんな理由で…」
人をこんな目に合わせていいのか!そう叫ぼうとしたものの、よくよく考えてみればレオナという人物はこういった人物だった事を思い出した。
どうせ今回だってダイとポップの為と言うものの、女に変わった自分を見た2人の反応を見るのが一番の目的に違いない。
(まったく…姫には毎度毎度苦労させられる…)
ふぅ~とため息を吐き一気に脱力してしまったヒュンケルを余所に、ダイとポップは瞳を輝かせてヒュンケルを見詰めていた。
「しっかし俺はお前が女になっても、ムキムキマッチョな女になると思ってたから正直びっくりだぜ!」
「…ムキムキマッチョな女…」
「これで中身がヒュンケルじゃなきゃお近づきになりたいぐらいだな!」
たとえ元々女であったとしても、それは遠慮する…そう思ったヒュンケルだったが、口には出さないでおいた。
「でもホントに女の子なんだー。だって背もいつもより少し低いし、手足だってこんなに細い…」
「なのに出るとこは出てるなんて私達女の子に喧嘩売ってるみたいよねー」
「いや、別にそんなつもりは…」
じと…と、羨望の眼差しを向けてくるレオナと珍しい物を見るようなダイの視線に、ヒュンケルはつい自分の身体を隠してしまった。
「ホントホント!この胸なんかマァムより大きいんじゃね~?デヘヘヘ…」
「…ポップ…そんな目で俺を見ないでくれるか…」
レオナやダイとは違う、明らかに厭らしさを含んだ熱い視線を胸元に注いでくるポップに、言い知れぬ嫌悪感が沸いてきた。
そんな三人三様の視線を全身に受け、居心地悪そうにしているヒュンケルだったが、そんな事に気付かないダイは、更にヒュンケルのその大きな胸へと熱い視線を送っていた。
プルプル揺れて大きなスライムみたい…。
スライムって触るとプニプニしてて気持ちいいんだよな…。
ゴメちゃんとどっちが柔らかいかな?
と、そんな事を考えていたのだ。
だからついポロリとこんな台詞が飛び出してしまった・・・・・・
「でもホント大きいね…ねぇ、ちょっと触ってみてもいい?」
「「「えぇ!?」」」
一瞬にして凍りつく3人を余所にダイはニコニコ笑っている。
「ちょ、お前!!それはまずいだろ!!」
「そうよダイ君!!いくらなんでもそれはセクハラよ!」
「えーセクハラってなんだよー!ちょっとだけだからいいよね?ヒュンケル?」
「え!あー…その…」
まさかそんな事を言われるとは思ってもいなかったヒュンケルはうろたえた。
たが元々自分は女ではないのだし、ダイだってなにも厭らしい事が目的で触りたいなどと言ったわけではない。(そんなの目を見ればわかる)
ただ純粋に大きくて柔らかい物への興味があるだけなのだ。
そう考えると別に胸を触られる事など、大した問題ではないような気がする。
だからヒュンケルはこくりと頷いてしまった。
「わぁっ!ホントに!?やったー!」
「ちょ、ちょっと!」
「オイ!本当にいいのかよ!?」
「あぁ、別にかまわん。」
そう言うとダイが触りやすいように少しだけ屈んでやる。
「じゃー早速―♪」
プニュvv
ダイの小さな手が柔らかな肉へと沈んでいく。
「わ~!!すっごい柔らかい!それにプニプニで気持ちいー!」
「そ、そうか…?俺にはよくわからんが…」
「本当だよ!わーありがとうヒュンケル!」
「ちょっとダイ君だけなんてずるいわ!私にも触らせて!」
たまらずレオナまでもがヒュンケルの胸に触れてきた。
「わぁvホント!すっごく柔らかくて気持ちいい!」
「だろ?ゴメちゃんと同じぐらい柔らかいかもしれない!」
「それに柔らかいだけじゃなくてこのハリと弾力!ホント羨ましいわ~!」
きゃいきゃい言い合いながら楽しくヒュンケルの胸を触っている2人を余所に、ポップは1人仏頂面で3人を眺めていた。
「なんでいヒュンケルの奴。俺が触ろうもんなら間違いなくグランドクルス放つだろうに、あの2人だけは特別扱いしやがってよー!」
ケッと悪態をつくものの、要するにポップは羨ましいのだ。
いやポップだけではない。
世の中のほとんどの男はきっと羨ましいと思うのが正常なのだろう。
そんな風に皆で戯れているなか、ふいにドアの向こうでダイを呼ぶ声が聞こえた。
「ダイ様?こちらにいらっしゃいますか?」
「あ、ラーハルトどうしたの?」
どうやらこの声はダイの忠実なる部下のラ-ハルトのようだ。
「は!そろそろ勉強の時間だというのにお姿が見えなかったもので、侍女に聞いたところ姫の部屋に居ると聞き、こうしてお迎えに参りました。」
「えー勉強~?今ちょっと忙しいから後からするよー」
そう言って誤魔化そうとするダイだったが、部下兼ダイの教育係でもあるラ-ハルトが許すはずがありません。
「なりません!昨日もその様におっしゃって結局勉強されなかったではありませんか!」
「大丈夫だよ。今日はちゃんとするからー」
「いけません!なんと言おうと今すぐ!勉強して頂きます!」
「っう…でも…」
「失礼致します!!」
尚も食い下がるダイに、これでは埒が明かないと思ったラ-ハルトは、ダイを無視して室内へと入っていった。
が、そんなラ-ハルトの目にとんでもない光景が飛び込んできた。
「ダ、ダイ様!一体何をされているのです!!」
それはなんと見知らぬ女の胸を思いっきり触りまくっているダイの姿だった。
「何っておっぱい触らせてもらってるんだよ。」
「そ、それは見ればわかります!それよりそのようなモノに触れてはなりません!」
「えーだって触ってもいいって言われたし…」
「いけません!今すぐおやめになってください!」
あの不埒な魔法使いならまだしも、己の大切な主がいくら下心が無いとはいえ、知らない者が見ればセクハラをしていると捉えてもおかしくはないだろう。
ダイの部下兼教育係兼生活指導係でもあるラ-ハルトがそれを許すはずがない。
「兎に角、お手をお放しください!」
「あぁぁ~!!」
無理やり胸から手を離させると、ダイは不満の声を上げたがそれは無視する事にした。
それよりも今はダイをこんな行為へと駆り立てさせた、この女に抗議をするのが先だ。
「貴様!そのような姿でダイ様を誘惑するとは!」
「え!いや別に俺誘惑されたわけじゃ…」
「いいえ!純真無垢なダイ様はこの女に惑わされたのです!」
どんな状況に置いても悪いのは全て相手でダイ様は悪くない!そう信じて疑わないラ-ハルトは、流石ダイ様の忠実な僕…。
「オイ女!二度とその様な姿でダイ様の前に現れるな!さもなくば…!」
ただじゃおかない!そう言い、ギリッと胸倉を掴み無理やり女の顔を上げさせた瞬間だった 、
ズキュ~~ン!!
ラーハルトの心臓を、何かが打ち抜けるようなそんな衝撃が走った!
「わぁ!ラ-ハルト大丈夫!?顔色が真っ青だよ!!」
「オイどうしちまったんだよオメ-!!」
みるみる顔を青くしていくラ-ハルトに、びっくりしたダイ達が声を上げるものの、ラ-ハルトにはまったく聞こえていなかった。
何故ならばラ-ハルトの思考の全て、視線の全てはただ一点、紫水晶のように澄んだ瞳をもつ女に釘付け状態だったからだ。
自分を凝視したまま益々青くなる顔色に加え、更には頬から湯気のようなものまで出始めたラーハルトを見て、流石に心配になってきたヒュンケルは声を掛けてみた。
「ラ-ハルト…?どうした大丈夫か?」
そう声を掛けると、ぴくりと動いたもののそれ以上の反応は無く、変わらずヒュンケルを凝視したまま完全に固まってしまっている。
「顔色が悪いぞ?どこか悪いのか?」
尚も心配するヒュンケルは固まるラーハルトの手に触れその瞳を覗き込んだ、が 、
「うわぁぁーー!!!」
「オ、オイ!ラ-ハルト!?」
物凄い勢いで手を振り払われてしまった。
心配になり手に触れたのがかえって逆効果だったのか、ラーハルトは手を振り払ったかと思うと、信じられないスピ-ドで部屋から飛び出して行ってしまった。
そのスピ-ドはというと、竜の騎士であるダイですら早過ぎてなにも見えなかったという…。
「…なんだったんだあいつは…」
「さぁー?わけわかんねぇけどすっげー顔色悪かったな…」
「うん…どこか身体の調子でも悪いのかな…」
「平気よ平気、心配しなくってもラーハルトはどこも悪くないわよ。」
ラーハルトが飛び出していった方向を3人は心配そうに見ていたが、レオナだけは3人とは違い、特に心配する様子もなくさらりとしている。
「姫さんは平気って言うけどあいつの顔色尋常じゃなかったぜ?」
「見た目は確かに真っ青だったけど、よく考えてみなさいよ。ラ-ハルトの血は青いのよ?」
「あ!!」
そういうレオナにポップはポンと一つ手を打った。
そう言われてみれば半分魔族のラ-ハルトの血は確かに青色だ。
「あーなるほどなー。そういえばそうだったなあいつ。じゃ真っ青だからって貧血おこしたわけじゃないって事だ!」」
「そっかーそれならとりあえず安心だね!」
一応自分の部下であるラ-ハルトの事を心配していたダイがほっと胸を撫で下ろした。
自分の事をこんなにも心配してくれる主の姿を見れば、きっとラ-ハルトは泣いて喜んだ事だろう…。
だが残念な事に彼は今この場にいない…。
「ふむ…しかしなぜ急にラーハルトは顔に血が上ったんだ?それに誰かに追われていたわけでもないのに、あんなに猛スピ-ドで出て行ったのもよくわからん…」
顔色の謎は解けたものの、ヒュンケルにはまだ疑問があったらしく、小さく首を傾げた。
「あ!そういやーなんでだろうなー?」
「別になにか驚くような事があったわけじゃないしどうしてだろうね…」
ヒュンケルの疑問にダイもポップもそうだそうだと頷くものの、肝心の理由については思いつかないらしく、同じように首を傾げている。
「ちょっとやだ!誰もわからないの?あんなバレバレだったのに!?」
そんな3人の様子をなんとなく見ていたレオナだったが、さも呆れた様な口調で言った。
「なんだよ姫さん!姫さんはわかんのか?」
「あったりまえじゃない!私はどっかの誰かさん達と違ってこういう事には敏感なのよ!」
特に他人の事に対してはね!…とは言わなかったが、要するにそういう事だ。
未だクエッションマ-クをいっぱい付けている3人を余所に、一人だけ今回の出来事に気付いたレオナは上機嫌で微笑んだ。
なんとあのラ-ハルトが一目惚れをしたなんて……普段は無愛想で無反応、恋愛のれの字も無さそうな彼が見せた以外な反応に、レオナは笑いが止まらない。
親友だと思っていた男が、まさか自分に恋をしてしまったなど気付かないヒュンケルが、この事実を知るのはまだまだ先になりそうだ。
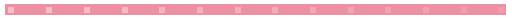
|
![]()