|
日が沈み夜の象徴である月が天高く輝く頃、ここカ-ル王国では盛大なパーティ-が開かれていた。
各国の主要メンバ-が集まるこのパ-ティ-には、パプニカを代表してレオナ以外にもアバンの使徒であるダイ・ポップ・マァム・ヒュンケルの4人も招待されていた。
「やぁー皆さんよく来てくれましたね!」
「いらっしゃい。今日は来てくれてありがとう。」
「アバン先生!フロ-ラ様!」
会場入り口に到着したレオナ達を笑顔で出迎えてくれたのは若きカ-ル王国国王アバンと、女王フロ-ラ夫妻だった。
「先生!フロ-ラ様!お久しぶりです!」
「今日はお招きありがとうございました!」
「いやー皆さん本当に久しぶりですね…元気でしたか?」
「はい!みんな元気に仕事に勉強にと頑張っています!」
「そうですか…それはよかった…」
笑顔で答える弟子達に、普段は国王としての顔のアバンも先生の顔へと戻り、変わらぬ弟子達の様子に心底嬉しそうに微笑んだ。
「でも仕事で毎日徹夜してるんで隈が消えなくって困ってるんだよな~」
「あら!ポップ君それじゃまるで私がこき使ってるみたいじゃない!」
「いや~あれはこき使ってる以外のなにものでもないと思うけどな…」
「俺で手伝える事があった手伝うよポップ~」
「あん?ダイ、お前はとにかく読み書きの勉強に集中してろ!」
「えーもう勉強飽きちゃった…」
「ダイ…辛いとは思うけどもう少しよ、頑張って。」
「マァム…ありがとう…」
優しいマァムの言葉にうるっとしてしまうダイは勇者といえどもまだまだ子供。
外で元気よく遊びたいお年頃なのだ。
「ハハハハ…相変わらずですね皆さん。」
まったく変わらない弟子達のやり取りをアバンは笑顔で聞いていたが、ふとその中に見知った人物がいない事に気付いた。
「そういえばヒュンケルはどうしたんです?彼も招待したはずですが…」
アバンにとって一番弟子であるヒュンケルの姿が見当たらないのだ。
「…もしかしてパーティ-なんて騒がしい所が嫌で来なかったとか…」
元々物静かで人ごみや騒々しい場所が苦手なヒュンケルならありえる話だ。
「そんな事ないですよ!今日は大事な日だから絶対に来るようにって命令しましたから!」
「そうですか、それならいいのですが…私も彼に会えるのを楽しみにしていたものですからね…」
そう言うと安堵のため息を吐いたアバンにレオナはにっこり微笑み言った。
「大丈夫ですよ先生!ヒュンケルの事だからいつの間にかふらっと現れて、隅っこの方にちゃっかり居たりしますよ♪」
レオナのおどけた言い方につい笑いが漏れてしまう。
「ふふふ…そうですね。それでは皆さん食べ物も飲み物もいっぱいありますので、おもいっきりパーティ-を楽しんでください。」
そんなアバンの言葉に弟子達が瞳を輝かせ大きく頷いた。
「はーい!俺もう超腹ぺこなんだよな~!」
「もぉーお行儀が悪いわよポップ!」
「俺もどんな料理がでるのか楽しみだったんだよねー」
「まったくうちの男の子達は食べ物の事しか考えないんだから…」
待ちきれなかったのか走って行ってしまったダイとポップに、やれやれといった感じのレオナとマァムだったが、彼らに続き賑やかな話し声が聞こえるパ-ティ-会場へと歩いていった。
それからどれほど時間が経っただろう・・・・・
月は輝きを増し、パ-ティ-会場の人々も美味しい食事とお酒にほろ酔い気分で上機嫌。
会場に響き渡る優雅な音楽に、あちこちから聞こえてくる明るい笑い声にと、皆がパーティ-を楽しんでいるのがよくわかる。
そんな和やかな雰囲気の中、一台の馬車がパ-ティ-会場へと到着した。
「……ん?何方かいらっしゃったみたいですね…」
「あらお1人…?女性の方のようだわ…」
会場の入り口から少し離れた場所にいるアバン達にははっきりとはわからなかったが、馬車から降りてきた人物のシルエットで女性だと思ったようだ。
「どこかのご令嬢かもしれませんね、私挨拶に行ってきます。」
「あら、あなただけなんて失礼よ、私も一緒にいくわ。」
パーティ-の主催者である2人が挨拶にいくのは当然と思っているフロ-ラに、「そうでしたね」と苦笑いを浮べ頷くと会場入り口へと歩き出した。
だが数歩ほど歩いた時、突然アバンもフロ-ラも歩みをやめ立ち止まってしまった。
その視線は会場入り口に注がれたまま、瞬き一つする事なく固まってしまっている。
「先生…フロ-ラ様…どうしたんですか?」
そんな2人に少し離れた場所からほろ酔い気分のレオナが声をかけるが返事はない。
「なんだか固まってるみたいだけど…大丈夫かしら…」
入り口を見たまま固まってしまっている2人に、意味がわからないと首を傾げるレオナとマァムだったが、今度は自分達の周りの変化に気がついた。
「ちょ、ちょっと皆どうしたのよ静かになっちゃって…!」
会場隅で今だ料理に夢中なポップとダイ以外、先程まで賑やかだった会場がいつの間にか水を打ったようにシ―ンと静まり返っているではないか。
あんなに上機嫌に酒を煽り豪快に笑っていた大臣も、音楽に合わせ優雅に舞っていた貴婦人も皆会場入り口を見詰めたまま固まってしまっているのだ。
いや正確にはたった今到着した1人の女性に皆の視線が注がれていたのだが……。
「誰か…来たみたいね…一体誰が来たのかしら…?」
レオナ達の位置からは遠くはっきり見えないが、明らかに彼女の出現によってこの場の空気は一変してしまったのだ。
困惑した表情のまま、問題の女性を近くで見ようと近づいていったレオナとマァムだったが、その存在がはっきりわかるにつれその顔には笑顔が戻っていた。
そう、その女性とは彼女達がよく知る人物であったからだ。
月明かりに照らされたその女性は、すらりとした長身に装飾品など付けずシンプルなロングドレスだけを身にまといながらも、まるで大輪の華の如く圧倒的な存在感をもった絶世の美女だった。
風に揺れる短い銀髪は、闇夜を照らすほどの輝きを放ち、紫水晶のような深い色を称えた切れ長の瞳に、極上の真珠を思わせるほどの白く滑らかな肌。
更に女性らしい豊かな胸の膨らみに括れたウエストと、成熟した大人の色香を漂わせている。
数多の美女すら嫉妬するほどの完璧な美貌と肉体をもったこの女性は、誰もが生身の女神に出会えたのだと思うほどの美しさだった。
彼女が歩けば人々の視線もその方向へと動く。
まさに釘付け状態といった感じだ。
そんな彼女がゆっくりとした足取りで皆の前を通り過ぎると、先程まで無言で固まっていた人々は弾かれた様に正気に戻ると、今後はざわめきへと変わった。
『お、おい!!一体今の美女はどこの何方なのだ!?』
『私の方が聞きたいぐらいですよ!!あんなにも美しい人を見たことがない!!』
『いやはやこれほどの美人がこの世にいるなど信じられんな…!!』
やんややんやと騒ぎ出した人々を、特に気にする事無く進んできた彼女だったが、アバンとフロ-ラの前まで来るとぴたりと歩みを止めた。
「先生…フロ-ラ様…お久しぶりです。」
落着いた静かな声でそう言うと、軽く会釈をし薄く微笑む彼女に、はっ!と我に返ったアバンが慌てて口を開いた。
「あ!え―…お初にお目にかかります!私は…」
「先生、そのような挨拶はやめにしませんか?」
そう言うとどこか照れくさそうに笑う彼女からは、とても初対面とは思えないほど落着いた雰囲気が伝わってきた。
まるで自分達はずいぶん昔からの友人や知人ですよ、といった感じだ。
(…あれ?…私…どこかで彼女と会いましたっけ??)
あまりの彼女の落着き振りに、初対面だと思っていたアバンは困惑した。
だがそれよりも彼女はもっと引っかかる単語を口にしていた。
でもこの子…私の事を『先生』と呼びましたよね…?
聞き間違えかと思ったものの、二度も呼ばれれば聞き間違えなどではない。
確かにこの女性は自分を先生と呼んだのだ。
という事は、この女性は過去に自分の弟子だったのか…?
(…い、いや私の弟子にこのような方は…それに私の弟子で女性はマァムと…レオナ姫だけのはず…)
困惑の表情のまま頭をフル回転させて考えるものの、どうにもこうにも思い当たる人物がいない。
(う~ん、私の弟子で長身に銀髪…といえば彼しか思いあたりませんが…)
一瞬浮かんだ一番弟子の顔だったがすぐに打ち消されてしまった。
(そもそも彼では性別が違いますし…いやでも他にとなると…)
う~と首を捻るものの、明らかに自分の事を知っていると思われるこの女性に「何処かでお会いしましたか?」などと聞ける雰囲気でもない。
全く思いあたらない…でもこのまま無言でいるのも失礼かと思ったアバンは、意を決して彼女に聞いてみる事にした。
「え―と、大変失礼かと思いますが…何処かでお会いしましたか…?」
「あ、それは…」
そう恐る恐る尋ねてみると、謎の女性が口を開く前に別の人物が大声を上げた。
「えぇー!先生本当にこの子が誰かわかんないんですか~!?」
「レ、レオナ姫!?」
「レオナそんな大声上げてはしたないわよ!」
いつの間にか自分の近くに来ていたレオナが、やけに意味有り気な笑みを浮かべアバンを見詰めている。
「レオナ姫!彼女の事知っているのですか?」
「知っているもなにも当然ですよー!ねぇ~マァム?」
「え?えぇ…まぁ…。でも先生がわからないのも無理ないと思いますよ…」
苦笑いを浮かべているマァムと、相変わらず意味深な笑みを浮かべているレオナの顔を交互に見比べた後、もう一度問題の女性へと視線を移す。
(…レオナ姫にマァムまで知っている人物…!?)
一体彼女は何者なのか…もてる全ての意識を集中させて記憶を遡ってみるものの、やはり思い当たらない…。
「ねぇ2人共、そろそろアバンに教えてあげてもらえないかしら?」
本気で悩み始めたアバンを見兼ねたフロ-ラが、2人に助け舟をお願いした。
「う~ん気付くと思ったんだけどな~」
「先生本気で困っているみたいだし、教えてあげましょうよ…」
「ん―…そうね、十分面白かったし♪でもきっと先生びっくりするわよ~」
そう言うと未だに女性の前で唸っているアバンに真実を伝えるべく声を掛けた。
「先~生♪どうしてもわかりませんか?」
「…うー…それは…」
「どーしてもわからいようでしたらお教えしてもいいんですがー」
どうします?と可愛らしく小首を傾げるレオナに、とうとうアバンはお手上げのポーズをとった。
「…申し訳ありません…姫、教えて頂けますか?」
そのアバンの言葉に満足したかのようにレオナは満面の笑みを浮かべると、はっきりした口調でこう言った。
「ヒュンケルですよヒュンケル♪先生の一番弟子ヒュンケルですよ~♪」
そう言うと「ねぇ~?」などと言いヒュンケルの顔を覗き込むレオナ。
「あ~ヒュンケル、あぁ…そう私の一番弟子ヒュンケルだったんですね~ってえ゛え゛ぇぇ!?」
ここがパ-ティ-会場だとか、王の威厳はどうしたとか、そんなもの全部殴り捨ててアバンはその場で絶叫した。
「アバン!!」
それを諌めるフロ-ラだったが、彼女の声はアバンには聞こえていなかった。
瞳を限界まで開き普段は微笑を絶やさない口元が今はあんぐり開いている。
「ヒュ、ヒュンケルですって!?私の知っているヒュンケルはこんな、こんな…!!」
胸とかバストとかおっぱいとかなかったはずですよ!!と大声で叫びかけたが、寸前のところでフロ-ラに口を塞がれた。
流石夫婦。
彼女には夫が言おうとしている事がばっちりわかったようだ。
そもそもアバンがうろたえながらも、目にも眩しいヒュンケルの豊かな胸の谷間を指差していたからなのだが…。
「先生!驚くのは無理ないかと思いますが少し落ち着いてください!」
「あーもう先生ってば最高のリアクショーン☆」
あわあわと慌てるアバンを、必死で落ち着かせようとしているマァムだったが、そんな彼女の横でレオナはただ目に涙を溜めてケラケラ笑っているだけで何も言おうとはしない。
これでは埒があかない
そう思ったマァムは、未だに混乱しているアバンに手短に事情を説明した。
レオナによって作り出された薬の事。
それを飲むと性別が逆転してしまう事。
そしてその薬をヒュンケルは飲まされた事。
それはとても信じられるような内容ではなかったが、今自分の目の前にいる人物を見る限り、それは真実だと信じざるを得なかった。
「…なるほど…そういうことだったんですね…」
幾分か落ち着きを取り戻したアバンは苦笑いを浮べつつ髪に手をやった。
どうやら先程取り乱した時に少々ヘア-が乱れてしまったようだ。
「先生…混乱させてしまい申し訳ありません…」
「いえいえヒュンケルが謝る事はないのですよ」
申し訳なさそうに上目遣いで謝るヒュンケルに、アバンはいつもの優しい笑顔で微笑んだ。
「そうよ!元はといえばレオナが無理やりヒュンケルに薬を飲ませたせいじゃない!」
「あらマァム、無理やりだなんて人聞きの悪い!ちょ~っとお茶に混ぜさせてもらっただけよ~」
「レオナから直々にお茶のサービスなんて怪しいって言っていたヒュンケルに、強引に飲ませのはレオナでしょ!?」
「…マァム、もういい。済んでしまった事はしょうがない。」
「…ヒュンケル…」
「そうそう♪結果すっごい美人だったんだし、先生をびっくりさせる事も成功したんだしもういいでしょ?」
まるで反省の色を見せないレオナに何か言おうとしたマァムだったが、そこをまたヒュンケルに止められてしまった。
まったく相変わらずヒュンケルはレオナには甘い 。
そう心の中で呟くマァムを、ヒュンケルは相変わらずの困った笑みで見詰めてくるだけだった。
「しかしこの薬はすごいですね~正直まだ貴方があのヒュンケルとは信じられないのですが…」
レオナから見せてもらった薬をしげしげと眺めつつアバンは言った。
「俺とて信じたくはないが、これが事実なのだから仕方がありません」
苦虫を噛み潰したような表情でそう言うヒュンケルは、忌々しげにドレスの裾を摘み上げ足元を見た。
どうやら慣れない細いヒールに足が痛くなってしまったようだ。
「しかし流石ですね姫…あの~もしよければこの薬の作り方…教えて頂けませんか?」
そもそもそんな物作ってどうするという考えよりも先に、発明家としての気持ちが勝ったアバンは悪戯っ子のような表情でレオナに聞いた。
「うっふっふ~先生さえよければ作り方…お教えしますよ…」
「え!?本当ですか!?それは是非是非!」
アバンに負けないぐらい悪戯な笑みを浮かべたレオナが大きく頷いた。
こうしてパ-ティ-終了後、早速レオナから薬の作り方を聞いているアバンの姿があったとかなかったとか…。
そんなパ-ティ-から一週間が経った頃、ヒュンケルはレオナに呼ばれ王室にいた。
そして2人の目の前にはずらーと並ぶ大量の写真……。
「…姫…これは一体なんですか?」
大量の写真の中から1枚を手に取りヒュンケルは首を傾げた。
写真にはやたらと華美な装飾が施された服を着た、小太りで油ぎっしゅな顔の貴族風の男が、豪華なイスに座りカメラ目線でにやついているなんとも気持ちの悪いものが写っていた。
「お見合い写真よ。」
「は?」
「聞こえなかった?お・見・合・い・写真って言ったのよ。」
「…なぜそんな物がこんなに沢山…」
改めて大量に散らばる写真に目を向けたヒュンケルだったが、どうやらどの写真も王族か貴族かと思われる男達が、これでもかと派手に着飾った上にやたらとキメポ-ズをとったものばかりが写っている。
「これね、全部この前のパ-ティ-で女の子の貴方を見た人達から届いたものなのよ」
「ま、まさかこんなに沢山……」
「そのまさか!正直私もこんな事になるなんて思ってもみなかったわ…ヒュンケル、貴方責任持ってちゃんとお断りの返事書いてちょうだいね?」
「…俺が書くんですか…?」
「当たり前よ!だってこれ全部ヒュンケル宛なのよ?だったらヒュンケルが書くのは当たり前でしょ?」
「し、しかし一体なんと書けばいいんですか?まさか実は男でしたとは…」
「それは貴方が考えることよ!それから一応お断りでも丁寧に!失礼のないように書いてちょうだいね!」
そう言うと机の引き出しからペンと紙を取り出しヒュンケルに握らせると、「じゃ、頑張って~♪」とだけ言いさっさと部屋を出て行ってしまったレオナ。
1人部屋に残されたヒュンケル。
そして目の前の大量の写真。
元々青白いヒュンケルの顔が更に色を無くしていく……。
そしてその後ヒュンケルが三日三晩寝ずに返事を書いたのは言うまでもない。
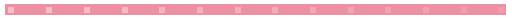
|